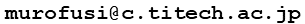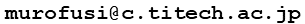[開設 07/31/23=MM/DD/YY]
概念束の作成手順
文脈表から紙と鉛筆で概念束を作成する手順
B. A. Davey & H. A. Priestley,
“Introduction to Lattices and Order”,
2nd ed.,
Cambridge Univ. Press,
p. 74
より (この書籍については
「参考書の紹介」
を参照)
-
Step 1 :
(G, M, I) のすべての外延を求める
-
-
(1.1)
-
2 列の表を作り,
列に
「属性」と「外延」という見出しを付ける
(属性-外延表).
第 1 行の属性欄には何も書かず,
外延欄にG と記入する.
-
(1.2)
-
文脈表のまだ削除されていない属性 m の中で,
m′ が極大なものを一つ選ぶ.
- (1.2.1)
-
m′ が
外延欄にまだ記入されていなければ,
m を新しい行の属性欄に記入し,
m′ を隣の外延欄に記入する.
外延欄の各外延と m′ との共通集合を取り,
まだ外延欄に記入されていないもの
について
新しい行を作り
外延欄に記入する
(その隣の属性欄には何も記入しない).
-
(1.2.2)
-
m′ が
外延欄に
記入済みの場合は,
m′ の
行の属性欄に m を追加記入する.
-
(1.3)
-
文脈表の m の列を削除する.
-
(1.4)
-
文脈表の列がすべて削除されれば終了.
削除されていなければ (1.2) へ戻る.
-
Step 2 :
m と m′ をラベルとする Hasse 図を描く
-
外延をラベルとするノードを配置し,
外延の包含関係に関する Hasse 図を描く.
属性-外延表で隣に属性のある外延をラベルに持つノードの脇に,
その属性をラベルとして記入する
(習慣では,外延や対象をノードの下に,
属性を上に書く).
-
Step 3 :
g と m をラベルとする Hasse 図に描き直す
-
-
(3.1)
-
Step 2 の結果の Hasse 図をもう一度描き,
属性ラベル m も同じ位置に記入する.
-
(3.2)
-
各対象 g ∊G について,
「Step 2 の Hasse 図で g を含む最小の外延のノード」と同じ位置のノードに g をラベルとして記入する.
-
Step 4 :
図のチェックをする
- (4.1)
-
どの結び既約な元も対象 g ∊G
のラベルを持っていることを確認する.
- (4.2)
-
どの交わり既約な元も属性 m ∊M
のラベルを持っていることを確認する.
- (4.3)
-
すべての属性 m ∊Mについて,
Hasse 図で m 以下の対象全体の集合が m′
に一致していることを確認する.
離散構造(室伏)のホーム